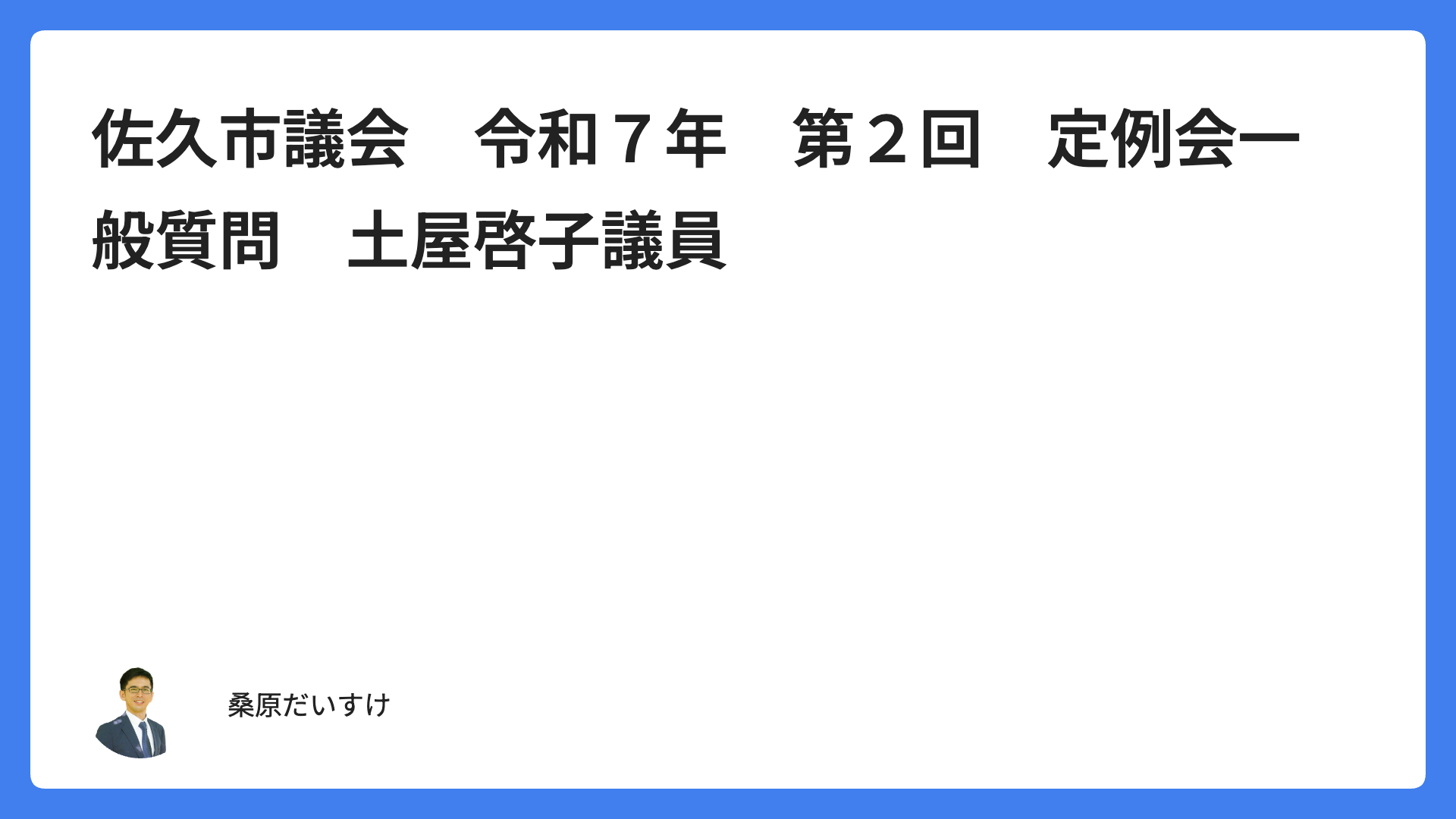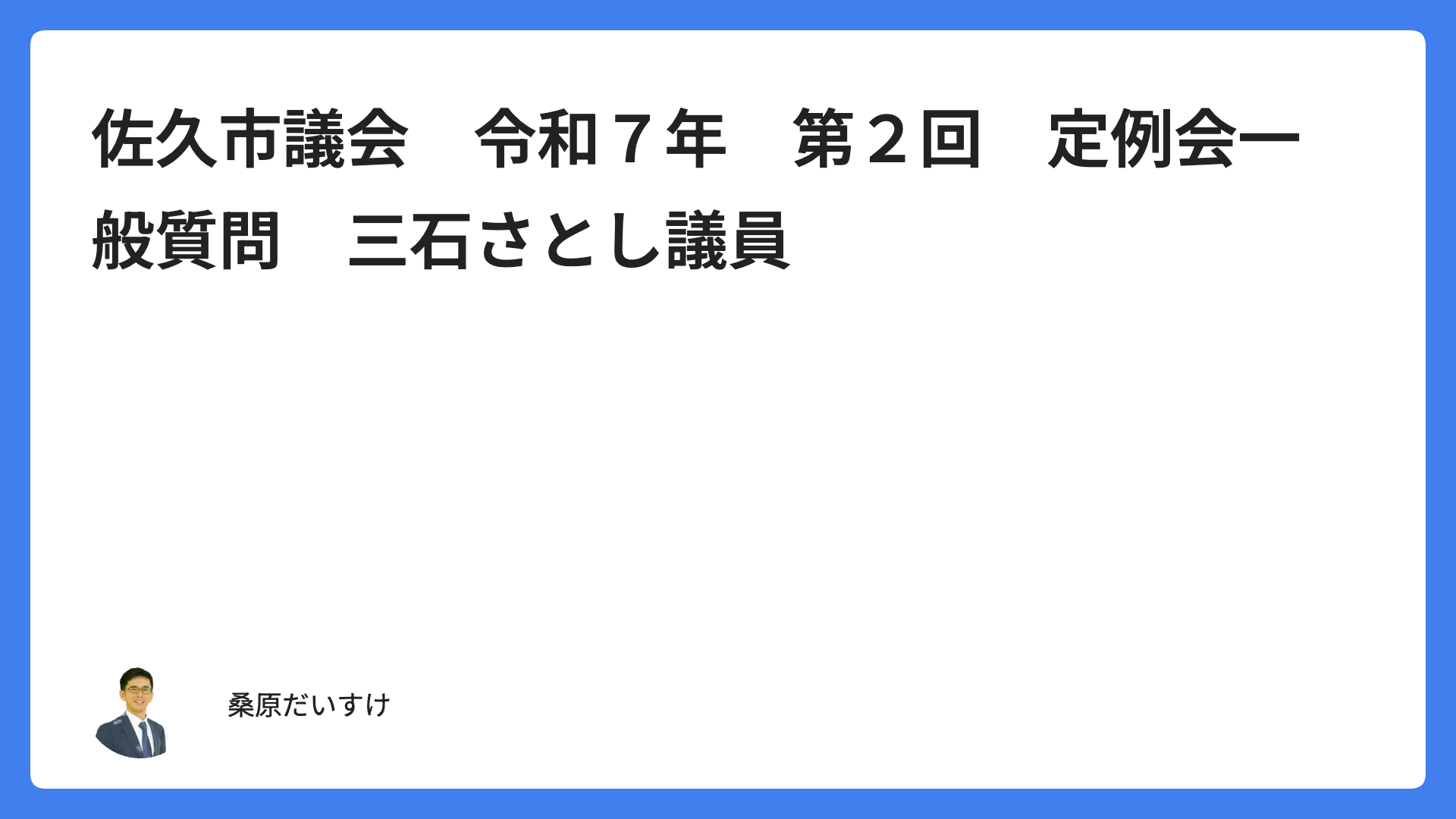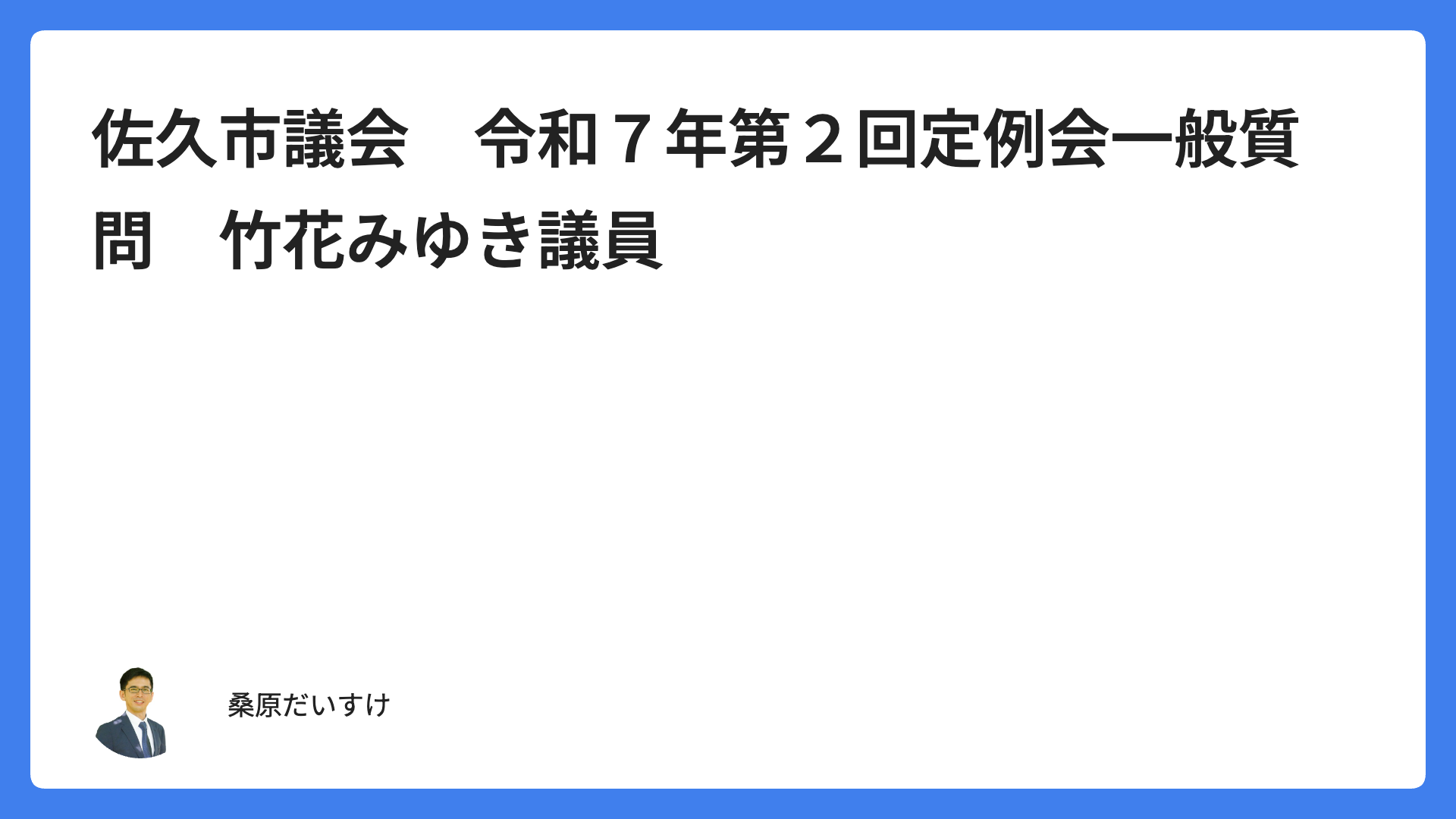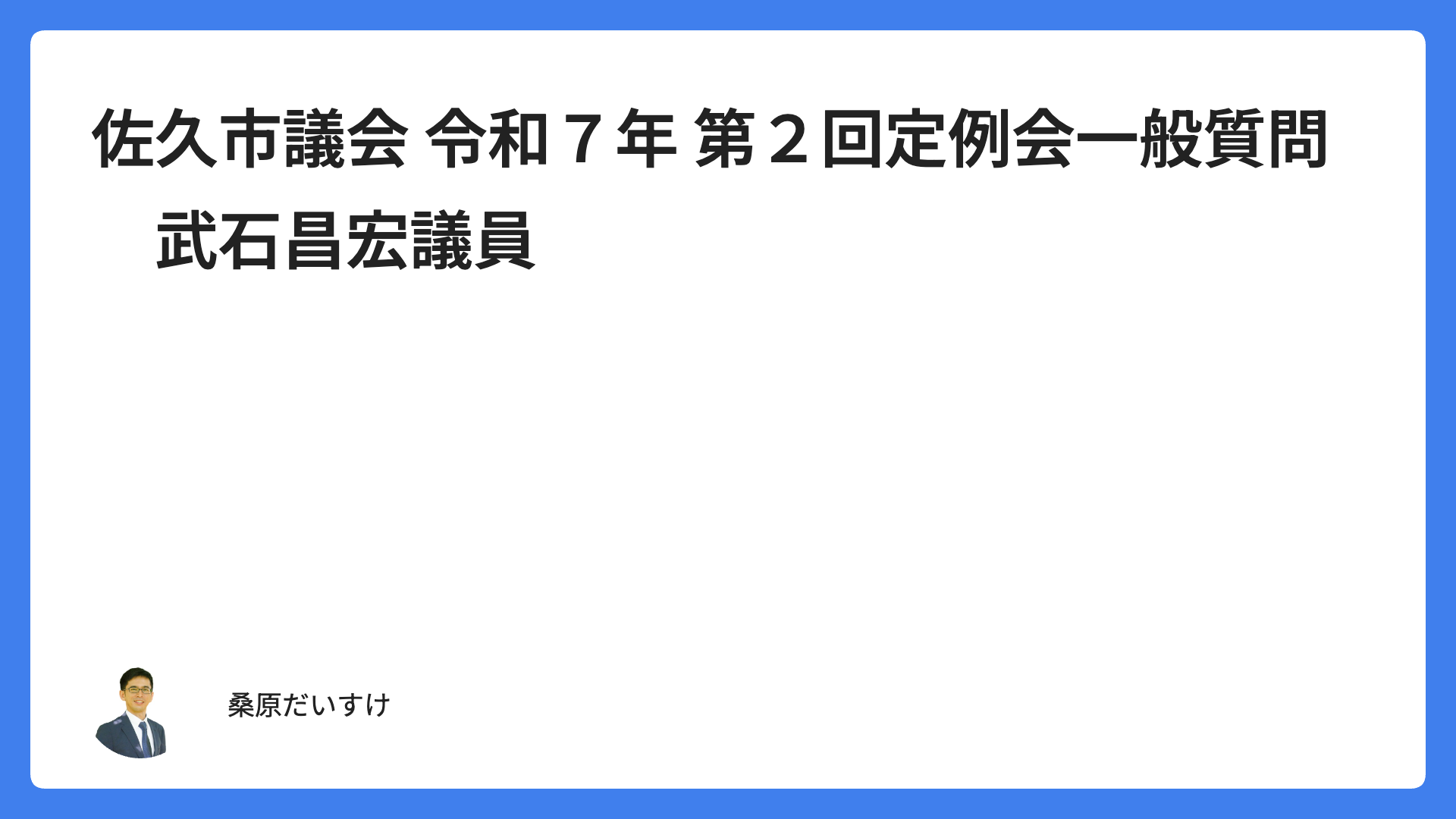佐久市議会 令和7年 第2回 定例会一般質問 栁澤大治議員
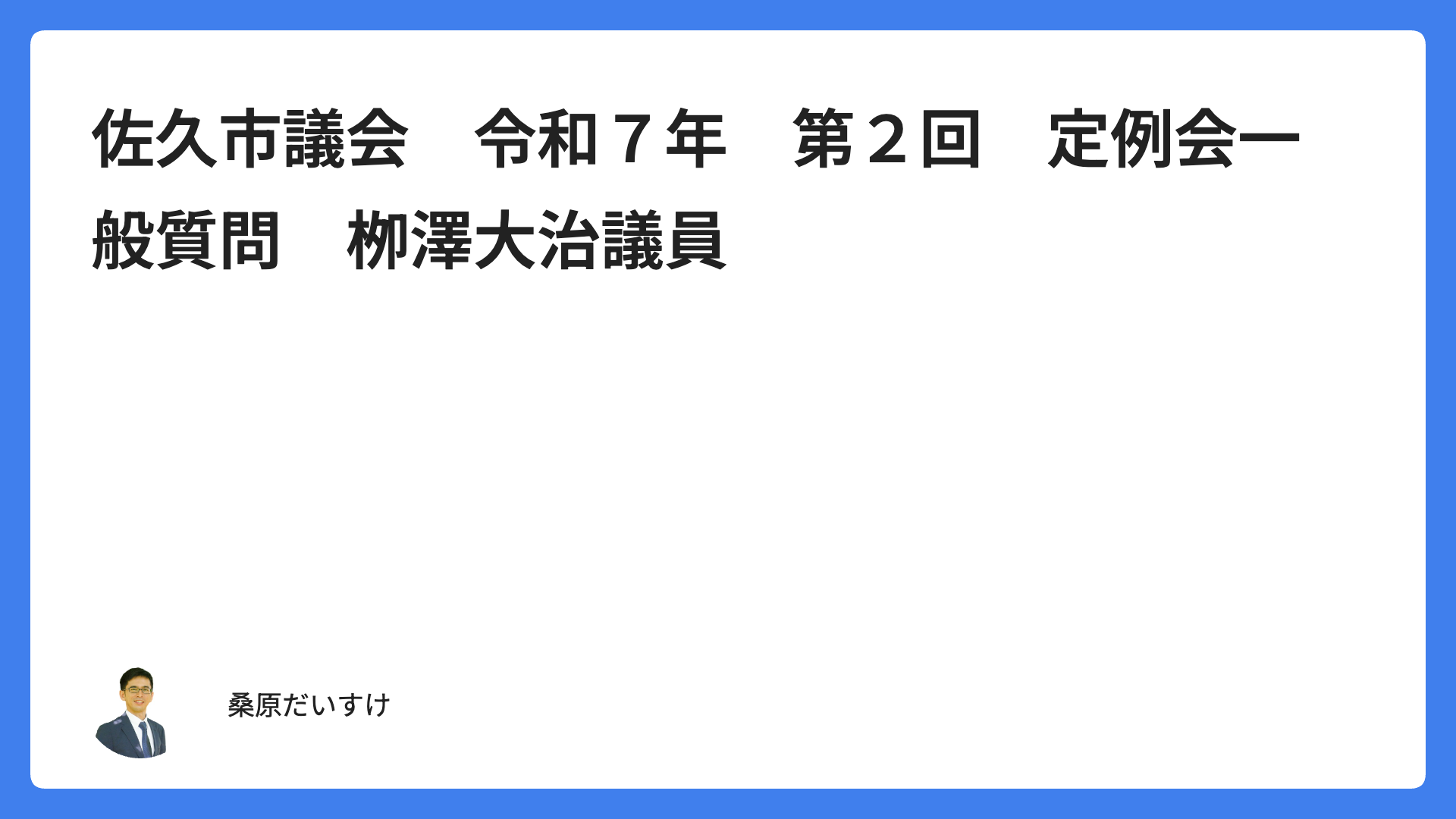
令和7年6月13日に実施された栁澤大治議員の一般質問の内容をまとめました。
・令和元年東日本台風の教訓を活かした河川災害対策
・全国的に進む部活動の地域移行
・デマンドワゴン「さくっと」の改善
について解説されていました。
1. 河川災害対策 – 令和元年東日本台風の教訓を活かして
あの時何が起きたのか
令和元年東日本台風では、佐久市でも甚大な被害が発生しました。特に滑川の堤防決壊は、多くの市民に深い印象を残しています。
被害の状況:
- 一級河川・滑川の堤防が決壊(杉の木地区・石神地区)
- 佐久市の観測史上1位の降水量を記録
- 国道141号を超えて浸水が拡大
- 下水道管理センターも浸水し、市の重要インフラに影響
決壊の原因:
- 記録的な大雨(佐久市だけでなく上流の長野県・群馬県でも)
- 石神地区の河川カーブで水勢が上昇
- 右カーブで水が左側に競り上がり、左岸堤防を浸食
完了した対策と今後の予定
すでに完了している対策:
- 腹付け盛土工法による堤防強化(延長1.05km)
- 堤防幅を3mから4mに拡幅
- 既存堤防を約1.5m嵩上げ
- 令和5年度に工事完了
今後の予定:
- 中部大橋から千間川合流点まで約1.4kmの区間で河川幅を広げる工事を検討
- 流下能力の確保が目的
市民を守る防災マップの整備
佐久市防災マップ:
- 平成24年度作成、令和2年度改定
- 100年に一度の大雨を想定
- 避難所、浸水想定区域、土砂災害警戒区域を掲載
佐久市洪水ハザードマップ:
- 令和4年度作成
- 1000年に一度の大雨を想定(より厳しい条件)
- 市内29の一級河川の流域ごとに作成
地域防災マップ:
- 各区が主体となって作成
- 地域の詳細な危険箇所や避難経路を記載
- 令和6年度末に目標の130区で作成完了
- 残り110区についても順次作成予定
これらのマップは「佐久の絆作戦」でも活用され、消防団と区が一体となった避難活動に役立てられています。
2. 部活動の地域移行 – 子どもたちの活動機会を守るために
なぜ地域移行が必要なのか
少子化の進行と学校の働き方改革の観点から、全国的に部活動の地域移行が進められています。佐久市では令和7年度末を目標に、休日の部活動を段階的に移行する方針です。
現在の取り組み状況
推進体制:
- 「佐久市地域スポーツ文化芸術活動推進連絡協議会」を設置
- 文化部も対象に含めて協議・検討を実施
モデルケース:
- 剣道とバレーボールで合同練習などを先行実施
- 現場の実情に応じた移行準備を進行中
指導者確保の取り組み:
- 令和6年3月から「地域クラブ指導者人材バンク」を設置
- 現在46名が登録(募集開始から着実に増加)
移行に向けた課題
場所と人の問題:
- 活動する場所の確保
- 指導者の確保(量と質の両面)
- 会場使用料、指導者謝金、保険料などの運営費用
競技特有の課題:
- 野球などの団体競技:部員数不足で市を越えた合同チームが必要
- 吹奏楽:楽器運搬や活動場所のセキュリティの問題
制度的な課題:
- 大会やコンクールへの参加方法
- 事故対応や不適切な指導への対応策
- 障害のある生徒への活動機会確保
「勝利至上主義」への懸念と対応
子どもたちが求めるもの: 令和6年1月のアンケート調査では、子どもたちが部活動に期待することは:
- 「楽しく活動したい」
- 「仲間を増やしたい」
市の方針:
- 競技力向上を目指すクラブと、楽しく活動するクラブなど多様な受け皿を整備
- 生徒が自分に合った活動を選べる環境づくり
- 学校部活動の指導方針を地域クラブと共有
保護者負担への配慮
現状の考え方:
- 地域クラブ活動の経費は原則として受益者(保護者)負担
軽減策の検討:
- 学校施設の継続的な利用による費用軽減
- 社会体育施設の活用
- 国や県からの財政支援の動向を踏まえた公的負担のあり方を検討
今後のスケジュール
改革期間の延長:
- 国の有識者会議が改革期間を令和13年度末まで延長する提言
- 佐久市も国の方針を参考に改めて検討
次回協議会:
- 7月4日開催予定の協議会で費用負担や会場確保への支援策を協議
段階的な移行:
- まず休日の受け皿確保に注力
- 平日を含めた完全移行は現時点で時期未定
3. デマンドワゴン「さくっと」の改善 – より良いサービスを目指して
乗り合い率の現状
乗り合い率とは: デマンドワゴン1台が1回運行する際に、複数人が乗車している状況の平均値
現在の状況:
- 令和6年度中の乗り合い率(小学生登下校利用除く):約1.4人
- 乗り合い率向上により単独車両が減少し、効率的な運用が可能
利用者への周知:
- 乗り合い運行は運行時間が長くなる場合があることを事前に説明
- 会員登録時の説明、出前講座、ホームページで周知
交通事故への対応
事故発生状況:
- 令和5年4月の本格運行開始から令和6年4月末まで:17件の交通事故
事故防止と対応策:
- 長野トヨタ自動車株式会社が「事故・緊急時対応の流れ」を作成
- 年1回、ドライバー対象の交通安全講習会を実施
- タクシー事業者と管理者による定期的な情報共有
利用者マナーの向上も課題
議員からは、「さくっと」が市民の重要な足として定着している一方で、無断キャンセルや不適切発言といった利用者側のマナーについても改善が必要だと指摘されています。
運行事業者と利用者が互いに尊重し合える、より良い地域交通として発展させていくことが期待されています。
だいすけは、こう見た👀
河川災害対策について
安心できる点
滑川の堤防が3mから4mに拡幅され、1.5m嵩上げされたということは、同じような災害が起きても以前より安全になったということ。令和5年度に工事が完了したというスピード感もありがたいと思います。
感謝したい点
地域防災マップを130区で作成完了したというのは、すごい!各区が主体となって作成してくださったということは、地域の皆さんが自分たちの安全について真剣に考えてきたということ。消防団と区が一体となって活動してくださっているのも心強いです。
お願いしたい点
防災マップは作っていただいたのですが、もっと積極的な周知をしていただけるとありがたいです。転入者への配布だけでなく、既存住民への定期的な配布や、出前講座の機会を増やしていただけると、より多くの方に防災意識を持っていただけるのではないでしょうか。
部活動の地域移行について
理解できる点
少子化と先生方の働き方改革という背景は、確かに避けて通れない問題だと思います。子どもの数が減っているのに、これまで通りの部活動を維持するのは現実的ではないかもしれません。先生方の負担軽減も大切ですね。
心配な点
保護者の経済的負担がどうなるのかが一番気になります。現在は「原則として受益者負担」ということですが、具体的にどのくらいの費用がかかるのか、家計に与える影響が心配です。特に複数のお子さんがいる家庭では大変そうです。
指導者の質についても不安があります。人材バンクに46名登録していただいているのはありがたいのですが、コンプライアンス研修を受けても、学校の先生と同じレベルの指導ができるのでしょうか。特に近年では「叱る指導」は効果が薄い。という研究結果もあります。
コーチング研修など、ソフト面での支援も必要ですね。
希望したい点
移行期間が令和13年度末まで延長されたということなので、もう少し時間をかけて丁寧に進めていただけるとありがたいです。特に、学校施設を継続的に利用できるようにしていただけると、費用負担も軽減されそうです。
また、平日を含めた完全移行についてはまだ時期が未定ということですが、働く保護者としては平日の対応も気になるところです。
デマンドワゴン「さくっと」について
ありがたい点
市民の足として定着しているのは本当にありがたいことです。高齢者の方々にとって、自家用車に頼らない移動手段があるのは心強いと思います。いつか自分も歩む道。
気になる点
年間17件の交通事故というのは、少し多いように感じます。1ヶ月に1件以上のペースで事故が起きているということですから、安全対策をもっと強化していただけるとありがたいです。
乗り合い率1.4人ということは、多くの場合1人で利用されているということですね。効率性を考えると、もう少し乗り合いが増えると良いのかもしれませんが、利用者としては待ち時間が長くなるのは困りものです。